| 5 前次 戻る |
 |
下から見上げる視線に、男の人って弱いんです。わたしは上目遣いで彼に笑いかけ、大きく口を開けてそれをほおばりました。
「う、ううっ……お、大野、さ、ん、っ」 「ん、んっ、んむ、んっ」 両手も休めないように、唇と舌も一生懸命動かして。頭上に感じていた斑目さんの視線が途切れます。目をつぶったのでしょうか。 彼の手がわたしの肩に回されました。片手はわたしの頭を撫でてくれます。なんだかそれが嬉しくて、わたしは動きをより早めました。 あまり下品にならないように気をつけていましたが、口の端からよだれが垂れてしまい、それでより滑りがよくなります。 「ん……ぁ……ちょ、大野さん、待、っ」 彼の腹筋に力が入るのが判りました。あ、出るんだ、と判りましたががかまわず――むしろ、さらにはげしくしゃぶります。 「だッ……んっ、く、大野さ――」 わたしの頭を撫でる手の力が、強まったり弱まったりしています。突き飛ばすわけにも行かず困っているのでしょう、そんなしぐさがまた可愛らしいです。――と、ついに我慢の限界に来たみたいです。 「く、ぁ、あ、あふ……ッ」 小さく呻くと、斑目さんはピークに達しました。どれほど我慢していたのでしょうか、ちょっとびっくりするような量の体液がわたしの口の中に注ぎ込まれます。 「んぷ……ぅう、んくっ」 やり場に困っていた彼の手は、結局わたしの頭を支えることにしたようで、おかげで動けなくなったわたしは斑目さんのを口から出すこともできず、あふれてこぼれた液体は頬やあごをつたって胸に白い水溜りを作ります。 「うわわっ、ごめん大野さん」 失敗を悟った斑目さんがヘッドボードからティッシュを持ってきて、わたしの体を拭いてくれました。 「けほ、斑目さん、いいですよぉ、そんなことしなくて」 彼のフットワークがあまりに良くてつい苦笑しながら、受け取ったティッシュで自分の体を拭きます。飲んであげようと思ったんですけど、失敗してしまいました。 |
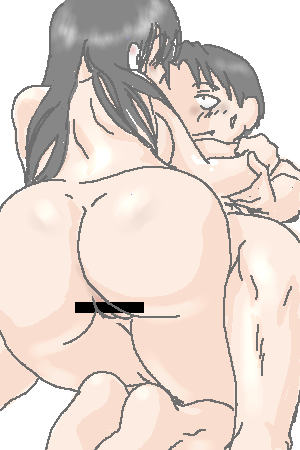 |
「どうせまた、あとでシャワー浴びるんですから。ふふ、それより」
「?」 「これで1対1ですね」 「ええ?これってそういうモン?試合?」 一段落したと思って、彼も自分のペースを取り戻しつつあるようです。 「あらぁ、知らなかったんですか?これからわたしの怒涛の快進撃が始まるんですよ」 「うわ、カンベン」 「勘弁しませんっ」 再び体をベッドの上へ。今度はわたしが斑目さんを押さえつけた状態から、二回戦の始まりです。……あれ、わたしが上?もう。 「……斑目さんたら、ホントに総受けなんですねー」 |
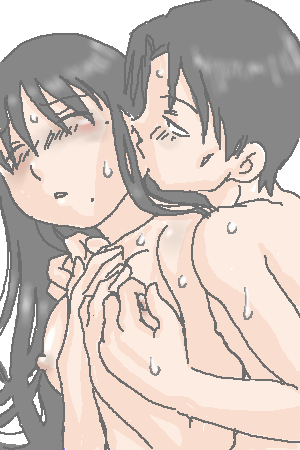 |
「ナンスカ」 「またわたしが押し倒してるじゃないですかぁ。自然にそういう体勢になってるのがおかしいんですよ」 「でも俺、今日はけっこう頑張ってる方だよ?」 ころん。斑目さんは挑発に付き合ってくれ、体を入れ替えてわたしを組み敷きました。 「ま……っ、斑目さん」 「うん」 「今度は……、もっと、激しくしてください、ね」 「大野さんはさ、激しくされるの、好きなの?」 「……ハイ」 「ん?ハイって、なに?」 「ゃ……ぁ」 「ちゃんと説明してくれなきゃ……わからないよ」 「ぅく……わたし……斑目さんに……いっぱい」 「いっぱい、なに?」 「いっ……ぱい、えっちなコト、して欲しいです……」 「えっちなコトって?」 本人のセリフの通りでした。斑目さん、いつもと違って、強気です。 |
 |
「たとえば……大野さんのおっぱい、いじったり……?」
首筋に舌を這わせながら、さっきみたいに胸を揉みしだいて。 「……ん、っ」 「たとえば、耳たぶ、噛んでみたり?」 顔の脇で、ほんの少し強く耳を噛んで。 「あ!」 「たとえば……たとえば」 今度はわたしの肌を味わいながら、どんどん下へ下へ降りてゆきます。唾液の軌跡はぬらぬらと光りながら、胸の先端を通り、肋骨の段差を越えて、おへそのすぐ脇を通り、…… 「……たとえば、ここ、開いて、みたり……?」 「ふぁ……はあ、っ……ん、んっ」 ヘアの茂みを分け入って、その先の割れ目にたどり着き……指で開いて、舌を差し込んできます。 ぴちゃ、ぴちゃっ、と、いやらしい音が聞こえます。割り箸で水飴でも練っているような、雨に濡れるあじさいを渦牛が這うような、蘭の花の蜜が床に垂れ落ちるような。 「大野さんの、ここ……」 「ぁ……や……ま、だ、ら、め……さ……」 「熱くて……やけどしそうだ」 「あ、あっ……ふ、うぅう……ん」 斑目さんの唇こそ熱くて熱くて、わたしの下半身が溶けてしまいそうです。ほんの数十分で目覚しく上達した彼の愛撫に、わたしのために優しくしてくれるその喜びに、視界が潤んできます。 「大野さん……脚、上げる、よ?」 「あ……やぁ……はっ、恥ずかし……」 斑目さんはわたしの両脚を大きく広げ、その舌はさらに深く強く攻め入ってきます。 あまりの羞恥に涙がにじみます。一刻も早く脚を閉じたいのに、わたしの両手はわたしを裏切って……斑目さんを手助けするように、わたしは自分で脚を抱え上げてしまいました。 |
 |
「ふっ、ふうっ、お、大野、さん……」 「あ……あ……斑目、さん、わたし……わたし、もう……ッ」 はしたない格好のままで、斑目さんに呼びかけます。 「お願い……です」 斑目さんが顔を上げました。わたしの脚の間で、胸とお腹の先に見える彼の顔はとても優しく、そしてとても意地悪に微笑みます。 「何を、お願いなの?大野さん」 |
前次 戻る |